内容証明「返信の書き方」回答書作成ガイド!来た場合の上手な対応術
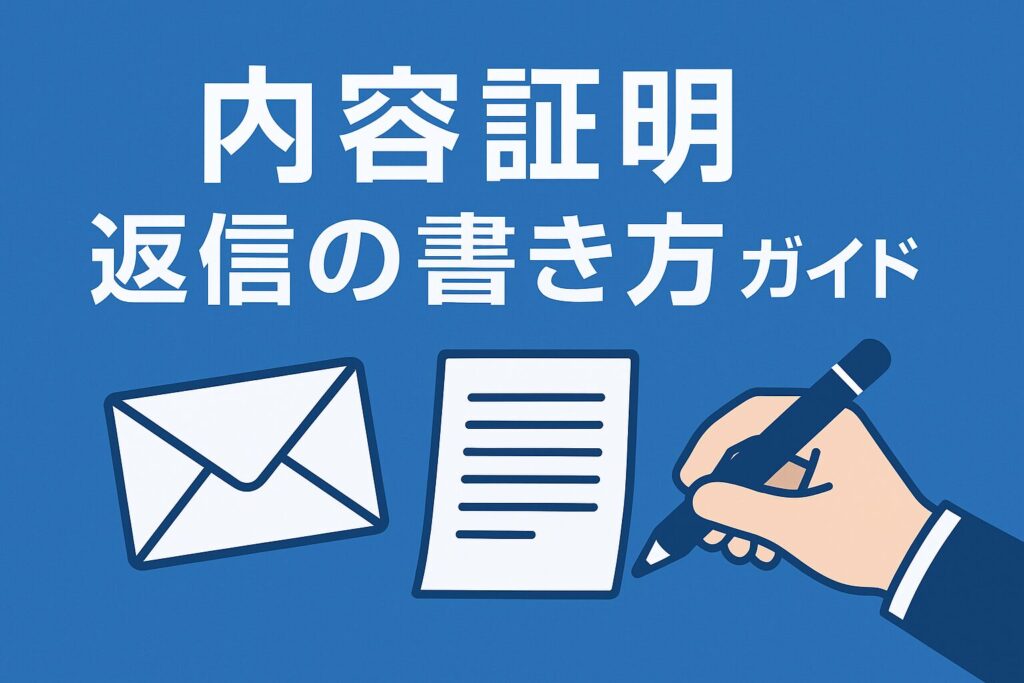
内容証明の「回答書」書き方ガイド|返信の基本構成・NG例・送付方法まで
内容証明郵便が届いたら、いちばん大切なのは「感情で返さない」「証拠を守る」「期限を落とさない」の3点です。
本記事は、内容証明に対する“回答書(返事の書面)”を作るときに迷いがちなポイントを、実務の流れに沿って整理しました。
※本記事は一般的な解説です。個別事情で結論が変わるため、重大案件は専門家へ相談してください。
1. そもそも「回答書」とは?(返信との違い)
回答書とは、相手が送ってきた通知書・請求書・催告書など(内容証明を含む)に対して、 こちらの立場(認める/否認する/条件次第で応じる等)を書面で公式に表明する文書です。
- 目的:「受領した事実」+「争点」+「結論(対応方針)」を記録に残す
- 効果:後日の交渉・裁判になった場合でも、当時の立場を説明しやすい
- 注意:不用意な“自白”や曖昧な表現は、相手に有利な証拠として使われ得る
ポイントは、長く書かないこと。回答書は「作文」ではなく「争点整理の書面」です。
2. まずやること:受領直後の初動チェック
2-1 封筒・到着日の記録(ここが弱いと後で困ります)
- 封筒(外装)・同封物を写真で残す(宛名、差出人、消印、受付印など)
- 到着日・受領方法(手渡し/ポスト投函)をメモ
- 同封資料(契約書コピー、請求内訳等)があるなら欠落がないか確認
2-2 内容物の“読み方”(焦ると見落とします)
- 何を求めているか:支払、謝罪、差止、契約解除、回答期限など
- 期限:「◯月◯日までに回答」等の明記の有無
- 根拠:契約条項、出来事の日時、証拠の提示の有無
- 差出人:本人か代理人(弁護士等)か/連絡窓口はどこか
2-3 返信前に“絶対やらないこと”
- 電話で口頭決着(言った言わないの火種)
- SNS/チャットで感情的に反論(スクショで残ります)
- 事実関係が不明のまま謝罪・支払約束(不利な自認になり得ます)
3. 回答書を出すべきか?判断フレーム
「必ず回答書が必要」ではありません。ただし、内容証明は相手が“次の一手”を考えていることが多く、 無視が不利に働くケースもあります。迷ったら次の観点で整理します。
3-1 回答書を出した方がよい典型例
- 期限付きの請求(支払・回答期限)がある
- 高額請求、信用・営業に影響する主張(風評、差止、契約解除など)がある
- 相手が弁護士名で送付している/訴訟・仮処分等の予告がある
- 事実誤認が明らかで、放置すると既成事実化されそう
3-2 いったん“保留回答”が合理的な典型例
- 資料が手元にない/社内確認が必要で、期限までに判断できない
- 相手の主張が抽象的で、こちらが答える前に相手へ具体化を求めたい
- 交渉窓口(代理人の有無)を整理してから対応したい
※保留でも「受領したこと」「検討中であること」「回答予定日」は書面で残すのが安全です。
4. 回答書の基本構成(テンプレの“型”)
回答書は、基本的に“型”で十分です。むしろ、型に収めたほうが不要な失点を防げます。
4-1 回答書の基本テンプレ(見出し構成)
- ① 日付
- ② 宛先(相手の氏名・住所/代理人宛の場合は代理人情報)
- ③ 差出人(自分の氏名・住所・連絡先)
- ④ 件名(例:
通知書(内容証明郵便)に対する回答書) - ⑤ 本文
- 受領の事実
- 立場の表明(全面否認/一部認める/条件提案/検討中)
- 争点ごとの簡潔な理由(必要最小限)
- 今後の連絡方法・期限(書面のみ、代理人宛て等)
- ⑥ 署名・押印(任意)
4-2 “短くするコツ”
- 争点は箇条書きで分ける(事実/法律評価/金額)
- 相手の主張を全文引用しない(必要部分だけ)
- 「反論」より「立場の明示」を優先(感情的な説教は逆効果)
4-3 安全な定型フレーズ例(丸写しOKの“骨格”)
※事実関係や金額等は必ず個別に調整してください。ここは“言い回し”の例です。
- 受領:
貴殿(貴社)より令和◯年◯月◯日付通知書(内容証明郵便)を受領しました。 - 否認:
通知書記載の主張は事実に反するため、当方はこれを認めません。 - 一部認容:
通知書記載のうち、◯◯の点については認めますが、◯◯の点は認めません。 - 交渉:
早期解決の観点から、条件次第では協議に応じる用意があります。 - 窓口:
今後のご連絡は書面にてお願いいたします。
5. 立場別:否認/一部認める/和解提案の書き分け
5-1 全面否認(争う)
全面否認は「何を否認するか」を明確にします。 例:事実(出来事自体)を否認/法的評価(責任の有無)を否認/金額(相当額)を争う、など。
- 否認対象を限定し、断定しすぎない(証拠精査前の断定は危険)
- 根拠は“必要最小限”で(長文の弁論は不要)
- 証拠があるなら「提出可能」で止め、全部さらさない(戦略的に)
5-2 一部認める(落とし所を作る)
一部認める場合は、認める範囲を曖昧にしないことが重要です。 「どこまでが事実」「どこからが評価」の線引きを意識しましょう。
- 認める事実を限定列挙
- 「謝罪=法的責任の全面承認」にならないよう、表現を整える
- 金額や条件に言及するなら、清算条項(これで解決)まで見据える
5-3 和解提案(分割・減額・接触禁止など)
和解提案は「金額」だけでなく、再燃を防ぐ条件がカギになります。
- 支払:一括/分割(回数・期日・振込先)
- 相互:今後の連絡方法/接触禁止/口外禁止
- 最重要:合意後は追加請求しない等の“終わらせる条項”
6. 絶対に避けたいNG表現・やりがちミス
6-1 NGになりやすい典型例
- 事実関係が確定していないのに謝罪(「全面的に私が悪い」等)
- 支払義務を認める断定(「必ず払います」「責任を認めます」等)
- 感情的な非難(脅し返し、侮辱、名誉毀損リスク)
- 曖昧な約束(「近いうちに」「なるべく早く」→揉めます)
- 余計な情報の開示(相手の主張を補強する材料を自分で出す)
6-2 “安全運転”の書き方チェック
- 書く前に、争点を3つ以内に圧縮できているか
- 日時・金額・相手方名などの客観情報に誤りがないか
- 相手の主張を“引用”しすぎていないか(こちらの文書が相手の台本になっていないか)
- 「認める」「謝罪」「支払う」の文言が必要以上に入っていないか
7. 期限が短い/資料がない:猶予(期限延長)の伝え方
期限が短いときは、放置よりも“猶予のお願い”を先に出す方が安全です。 ここでも大事なのは「受領」+「検討中」+「回答予定日」です。
7-1 期限延長の定型フレーズ例
内容精査および関係資料の確認に時間を要するため、誠に恐縮ですが回答期限を令和◯年◯月◯日までご猶予いただけますようお願い申し上げます。回答の齟齬を防ぐため、必要資料を整理のうえ書面にて回答いたします。
8. 送付方法:普通郵便?簡易書留?内容証明で返す?
8-1 まず結論:重要度に比例して“記録が残る方法”へ
- 軽微:メール+念のため郵送(控え保存)
- 通常:郵送(配達記録・簡易書留など)
- 重大:回答書も内容証明(いつ・何を言ったかを強く残す)
8-2 回答書を内容証明で返すべき場面
- 相手が内容証明で強い主張(解除、差止、訴訟予告等)をしている
- こちらも「立場表明」を明確に証拠化しておきたい
- 期限や到達が争点になりそう(いつ届いた/届いてない)
8-3 控え(証拠)の残し方
- 送った文書の最終版PDF
- 発送伝票・追跡番号・受領証
- 同封資料一覧(何を同封したかのメモ)
※「内容証明の手続は郵便局で行います。取扱局が限られるため、事前確認すると安心です。」
9. 実務フロー:社内(個人)での対応手順
10. Q&A(よくある質問10個)
Q1. 内容証明が届いたら、必ず回答書を出さないといけませんか?
A. 必須とは限りません。ただ、期限付き・高額・訴訟予告など不利益が大きい内容は、無視が不利に働くことがあります。迷うなら「受領+検討中+回答予定日」の保留回答を検討してください。
Q2. 電話で話して終わらせても良いですか?
A. 口頭は「言った言わない」が残ります。電話をするなら、要点を必ず書面で追認(メールや郵送)し、記録を残してください。
Q3. 回答書に「事実無根」とだけ書けば足りますか?
A. 不足になりやすいです。「何を否認するのか(事実/法的評価/金額)」を分け、必要最小限の理由を添えると争点が明確になります。
Q4. 謝罪を書けば早く終わりますか?
A. 早期解決につながる場合もありますが、謝罪が全面的な責任の自認と受け取られるリスクがあります。事実関係が固まる前の謝罪・支払約束は慎重に。
Q5. 相手が弁護士名で送ってきました。どう対応すべき?
A. 期限や請求根拠が整っていることが多く、放置は危険です。まずは争点整理をして、必要なら早期に弁護士へ相談しましょう。
Q6. 期限が3日後など短すぎます。間に合いません。
A. いきなり黙るより、猶予(期限延長)を依頼する書面を先に出すのが安全です。「受領」「検討中」「回答予定日」を明記してください。
Q7. 回答書は手書きでも良いですか?
A. 一般には手書きでも構いませんが、誤字・修正跡・控え管理の観点からはPC作成が無難です。いずれにせよ、最終版の控えは必ず保存してください。
Q8. 回答書も内容証明で送った方が良いですか?
A. 重大案件(解除・差止・高額請求・訴訟予告等)では有効です。一方、軽微な案件まで内容証明にすると、相手の対立姿勢を強めることもあるため、重要度で選びましょう。
Q9. 回答書に証拠(資料)は同封すべきですか?
A. 案件次第です。相手の誤解を解くには有効な反面、こちらの手の内を全部見せることにもなります。提出は「提出可能」として留める選択もあります。
Q10. 行政書士と弁護士、どちらに相談すべきですか?
A. 一般に、行政書士は書面作成(回答書・通知書等)の整備に強く、弁護士は代理交渉・訴訟対応が可能です。争いが大きい/代理が必要なら弁護士、まずは文書を整えたいなら行政書士、という整理が目安です。
11. まとめ:回答書で失敗しない優先順位
- 到着記録と証拠保全(封筒・同封物・日時の記録)
- 期限と要求内容の把握(何を、いつまでに、どうする?)
- 事実確認と争点整理(3つ以内に圧縮)
- 回答書は短く、型で(受領・立場・争点・連絡方法)
- 重大案件は早めに専門家(放置が最大のリスク)
回答書は「言い負かす文章」ではなく、「争点を固定し、不要な失点を防ぐ文書」です。
冷静に、短く、記録が残る方法で対応することが、最短での収束につながります。
※上のリンク(#contact 等)は、WordPress側で該当セクションや固定ページに差し替えてください。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配



