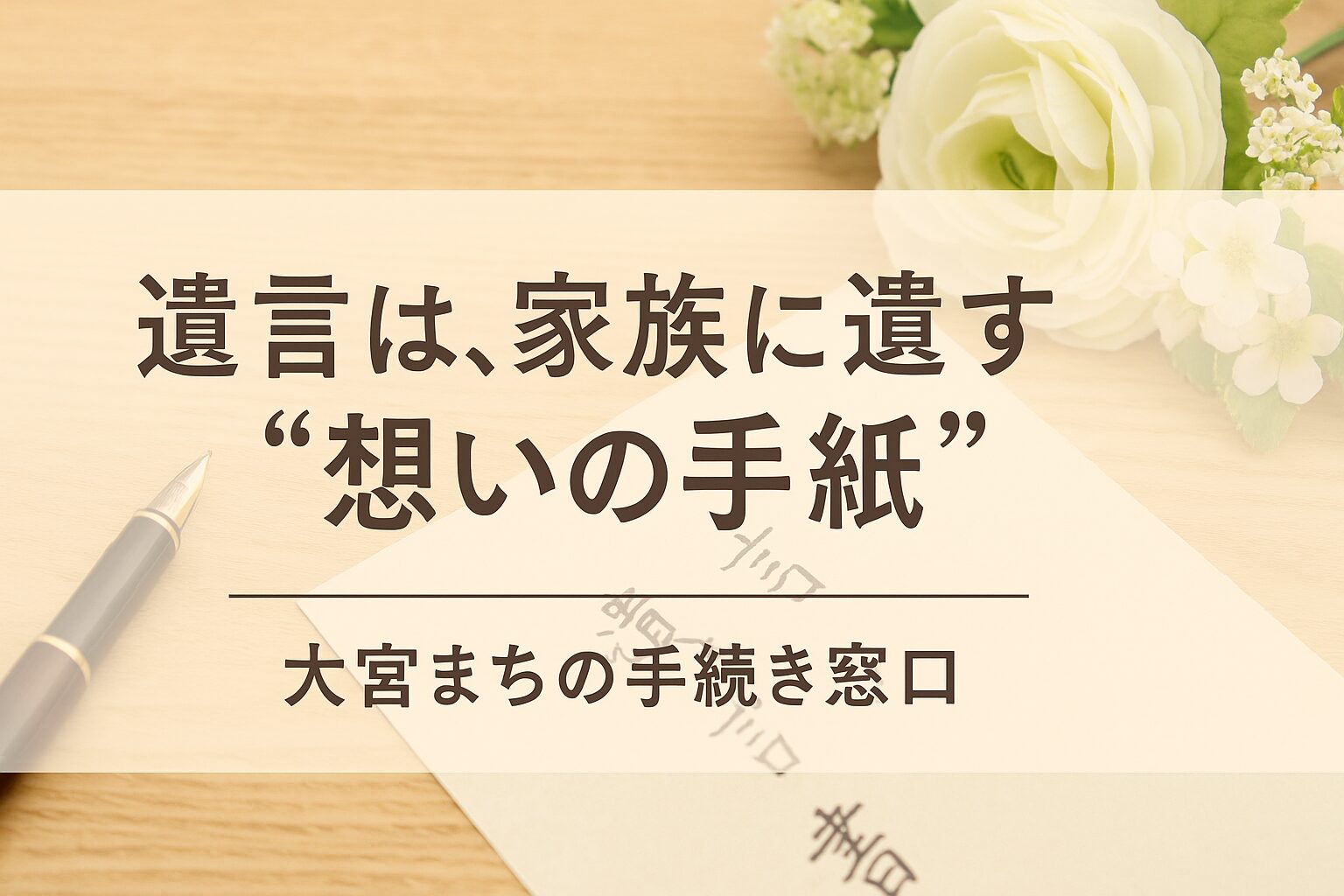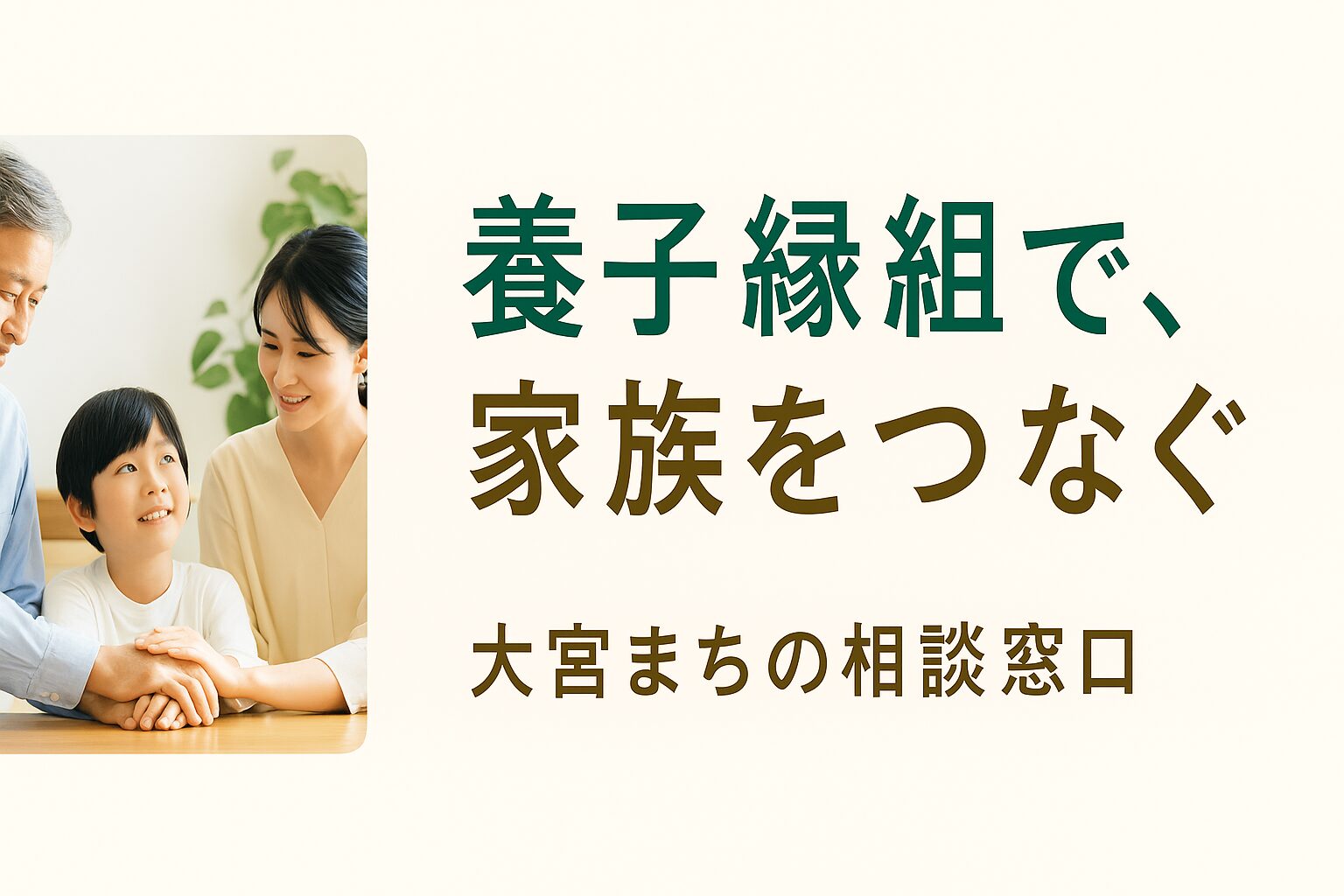ブラック相続シリーズ
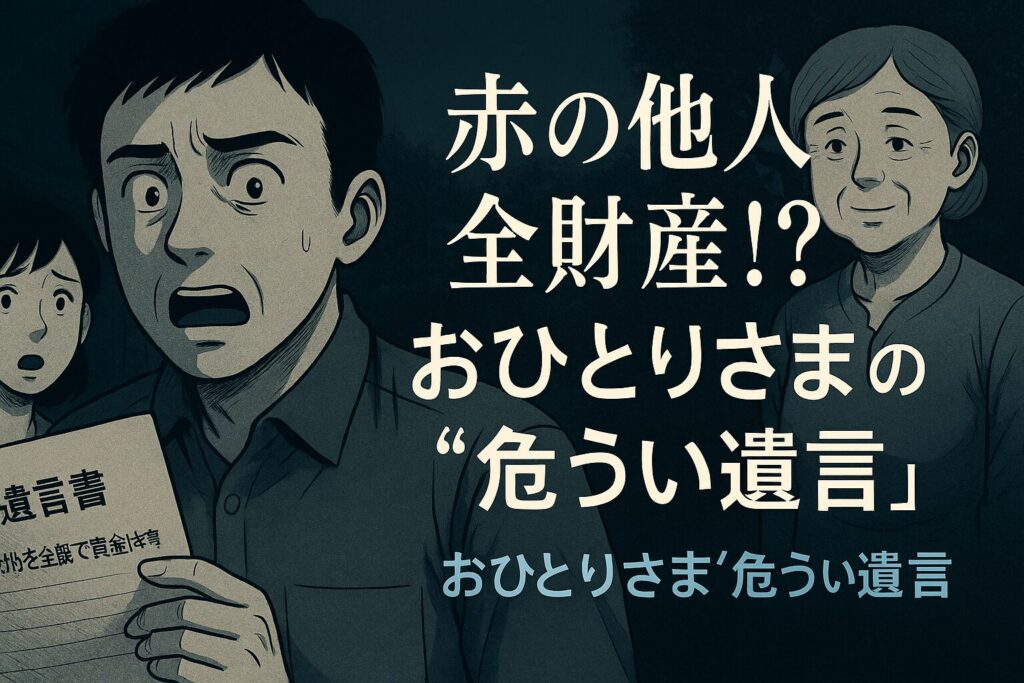
「遺言で財産が“赤の他人”へ?」信じられない通知
ある日、Aさん(40代・甥)のもとに届いた一通の手紙。それは亡くなった伯母の遺言執行通知でした。中を確認すると、「すべての財産を◯◯さんに遺贈する」と記されており、名前は近所でよく世話をしていた女性でした。Aさんは思わず言葉を失います——「自分は相続できないのか?」
法的に“他人”にも遺贈は可能
日本の民法では、遺言書が有効であれば、受遺者が誰であれ財産を譲ることが可能です。たとえ血縁関係のない近所の人や訪問ヘルパーであっても、遺言によって遺産を受け取る権利が生じます。
相続人(親族)にとっては納得しがたい内容でも、法的に有効な形式で書かれた遺言であれば覆すことは非常に難しいのです。
よくあるトラブル事例
- 介護ヘルパーに全財産が遺贈され、親族がまったく知らされていなかった
- 近所の人に遺贈された不動産をめぐって、甥姪が遺言無効の訴訟を起こした
- 「孤独だった高齢者が言いくるめられたのでは」と疑い、親族間で対立が勃発
特におひとりさまの場合、相談相手も少なく遺言の内容が偏ることがあります。
遺言ミスの防止策|おひとりさまこそ“公正証書遺言”を
高齢のおひとりさまが遺志を正しく反映させるためには、公正証書遺言の作成が最も確実です。公証人が内容を確認・記録するため、法的不備がなく、第三者による操作や偽造のリスクも低減されます。
また、信頼できる第三者(専門家や後見人など)と事前に相談することで、本当に望む形を検討することが可能になります。
遺留分の対象外に注意
注意すべきなのは、甥・姪などの親族は「遺留分」がないという点です。遺言に納得がいかなくても、法的に取り戻す手段がない可能性があるのです。
つまり、遺言によってすべての財産を“他人”に遺すことも可能であり、それを争うには「遺言能力の欠如」「詐欺・脅迫」などの厳しい立証が必要です。
まとめ|「誰に残すか」は最終意思でも“慎重に”
おひとりさまが増える中で、「赤の他人に全財産がいってしまった」という事例は決して他人事ではありません。意図せぬ誤解や争いを防ぐために、遺言こそ慎重に整備することが大切です。
将来のトラブルを避けるためにも、一度専門家に相談しながら、納得できる形で遺言を残すようにしましょう。