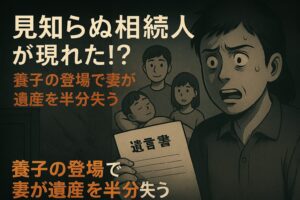ブラック相続シリーズ
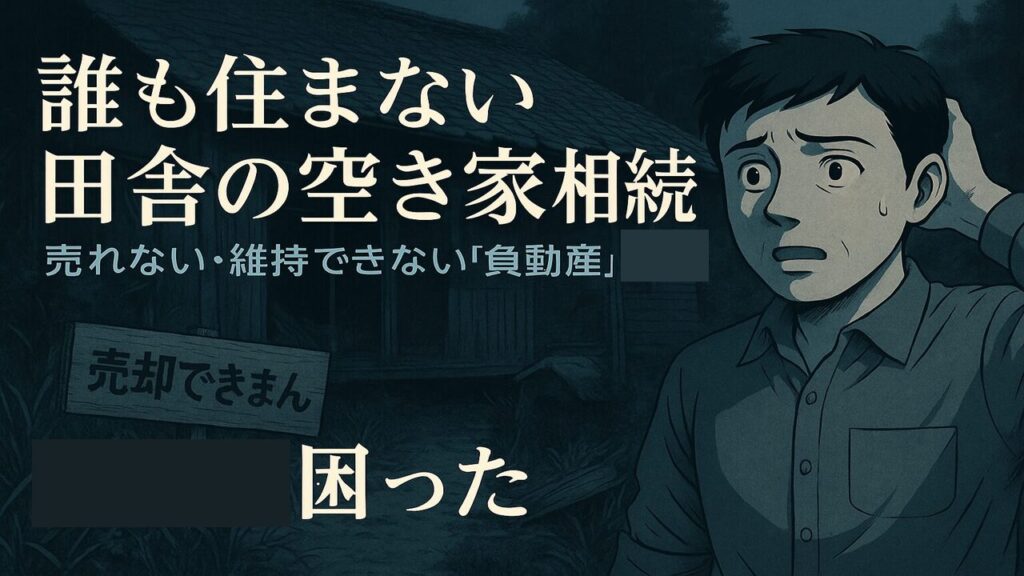
親の遺産で残されたのは…田舎の空き家
Aさんは都市部で暮らす30代の会社員。父の死後に実家を相続したものの、それは誰も住まない田舎の老朽化した家でした。
親族の中でも「誰が管理するのか」「売れるのか」といった議論はなく、結局名義だけがAさんに移ったのです。
使えない・売れない・管理できない“三重苦”
田舎の空き家には以下のような問題がつきまといます:
- 交通の便が悪く、買い手がつかない
- 草刈り・屋根修理・通風などの管理が必要
- 固定資産税や火災保険の支払いが続く
こうして、“負動産”としての空き家が相続人の負担となっていきます。
売却しようにも「売れない」現実
空き家バンクや不動産仲介に相談しても、「立地的に買い手がつかない」と断られるケースは珍しくありません。
また、建物の老朽化が進んでいる場合、解体費用を請求されたうえで“土地のみ”の売却を提案されることも。
結果として、売れないまま毎年税金と管理費用だけがかかる状態に陥るのです。
放置のリスク|近隣からの苦情・行政指導も
手を付けないままにしておくと、次第に草木が生い茂り、不法投棄や小動物の住みかになることもあります。
- 「景観を損ねている」と近隣から苦情
- 「空き家等対策特別措置法」に基づく行政指導・解体命令
- 地震・台風で倒壊した場合の損害賠償リスク
空き家対策の選択肢と実行ステップ
放置を避けるためには、以下のような対応が考えられます:
- 売却・空き家バンク登録(低価格でも手放せる可能性)
- 相続放棄(3ヶ月以内の申述)
- 市町村やNPOへの寄付交渉(条件あり)
- 家屋解体後の土地活用(太陽光・貸地)
特に「解体→更地」にすることで、選択肢が広がるケースもあります。
まとめ|“誰も住まない家”は財産ではない
親から受け継いだ家が、思い出ではなく「お荷物」になることは、いまや全国的な課題です。
「いずれ誰かが何とかするだろう」ではなく、“自分ごと”として向き合う姿勢が必要です。
相続前後で迷っている方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
状況に合わせた選択肢をご提案いたします。