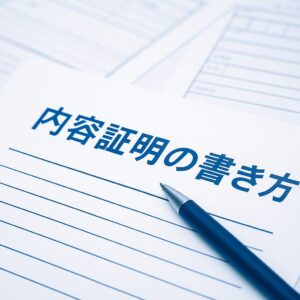e内容証明(電子内容証明)ってどう?書き方と手続きの流れをやさしく解説
e内容証明の登録・発送手続きをすべて代行します。
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。

WEB内容証明とは?紙の内容証明との違い
「WEB内容証明」とは、郵便局が提供している電子版の内容証明サービス(電子内容証明)を使い、インターネット経由で内容証明郵便を差し出す方法のことです。紙の内容証明と同じように、「誰が・いつ・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれますが、文書の作成や差出しをすべてオンラインで完結できる点が大きな特徴です。
相手に届くのは従来どおり紙の文書ですが、「送る側」がパソコンからデータを入力し、郵便局側でプリントアウトして相手に配達するイメージです。そのため、法的な効力は紙の内容証明と同じと考えて大丈夫です。ただし、使い方や画面表示が専門用語だらけで、郵便局HPだけではイメージが掴みにくいという声も多く聞かれます。
WEB内容証明を利用するシーン
例えば、仕事が忙しくて郵便局の窓口営業時間に行けない方、地方に住んでいて取扱郵便局が遠い方、複数の内容証明を継続的に送る事業者などには、WEB内容証明は非常に相性が良い方法です。一方で、「一度きりでいい」「IT操作が苦手」という方には、かえって負担になることもあります。
WEB内容証明のメリット
まずは、紙の内容証明にはないWEB内容証明ならではのメリットから整理してみましょう。
24時間いつでも差し出し手続きができる
最大の利点は、時間と場所を選ばずに手続きができることです。自宅や職場のパソコンから、夜間や土日祝日でも文書の作成・送信が可能です。締切ギリギリの交渉や、どうしても今日中に意思表示をしておきたい場面では、大きな安心感につながります。
郵便局に行かなくていい・待ち時間がない
紙の内容証明では、取扱いのある郵便局まで出向き、窓口で手続きをする必要があります。混雑していると30分以上待たされることも珍しくありません。WEB内容証明なら、窓口に並ぶ手間・移動時間・交通費がゼロになり、忙しいビジネスパーソンにとっては大きな時間短縮になります。
データで保存できるので管理が楽
WEB内容証明では、作成した文書や控えが電子データとして保存できます。PDF形式でダウンロードしておけば、紛失リスクが減り、あとから検索・再利用も簡単です。紙の控えをファイルで管理するよりも、案件が多い事業者にとっては圧倒的に効率的です。
レイアウトチェックをシステムが自動で行ってくれる
紙の内容証明では、「1行20字以内・1枚26行以内」といったレイアウトを自分で数えながら調整する必要があります。WEB内容証明では、システム側で自動的に行数・文字数を判定してくれるため、基本ルールさえ守っていれば細かい調整に悩まされることが減ります。
WEB内容証明のデメリット・難しいポイント
一方で、WEB内容証明には「便利そうだからと登録してみたが、途中で挫折した」という声も少なくありません。郵便局HPを見ただけではイメージしづらい、少し難しいポイントを整理しておきます。
アカウント登録と初期設定がややハードル高め
WEB内容証明を利用するには、まず専用サイトでアカウント登録を行い、住所・氏名・連絡先などの基本情報を設定します。さらに、料金支払いのためのクレジットカード情報登録なども必要になることが多く、「まず登録作業だけで疲れてしまう」という方もいます。
また、法人名義で利用したい場合は、担当者と会社情報の紐づけなど、紙の窓口手続きよりも情報登録が細かく感じられる場合があります。
システム画面と専門用語が分かりにくい
郵便局のWEB内容証明の画面は、どうしても「郵便事業の内部用語」が前提になっているため、初めて利用する一般の方には説明が回りくどく感じられます。例えば、
- 「差出人情報」「受取人情報」の登録順序が分かりづらい
- レイアウトの「様式」選択肢が多く、どれを選べばいいか迷う
- 書式エラーが出ても、何を直せばよいか説明が抽象的
など、画面上の言葉と自分の感覚がかみ合わないことが失敗の原因になりがちです。
文字数・行数・レイアウトのルール自体は紙と同じく厳格
WEB内容証明は便利ですが、そもそものルール(1行何文字まで、1枚何行まで、使用できる文字の種類など)は紙の内容証明と同じです。システムがエラー表示をしてくれるとはいえ、
- 改行位置によって意味が分かりにくくなる
- 長い数字や金額が途中で折り返されて読みにくくなる
- 全角・半角の混在で文字数カウントが変わる
といった問題は残ります。「機械的に通った=読みやすい文書」とは限らない点が難しいところです。
パソコン環境・ブラウザ設定の影響を受ける
WEB内容証明は、ある程度新しいパソコンと安定したインターネット回線が前提です。ブラウザの設定によっては、
- ポップアップブロックが働いて画面が開かない
- 作成途中でセッションが切れて、最初からやり直しになる
といったトラブルも起こり得ます。IT操作に慣れていない人にとっては、これだけで大きなストレスになるでしょう。
法律内容までは自動チェックしてくれない
WEB内容証明のシステムは、あくまでも「形式上のルール」を確認してくれるだけで、文書の内容が法律的に妥当かどうかまではチェックしてくれません。例えば、
- 請求の根拠があいまいなまま送ってしまう
- 感情的な表現が多く、かえって紛争がこじれる
- 相手の受け取り方によっては名誉毀損等のリスクがある
といった文面でも、形式さえ合っていればシステムは受け付けてしまいます。「WEBで簡単に送れる=内容も適切」というわけではない点が、実は一番の落とし穴です。
Q. WEB内容証明なら、郵便局が内容をチェックしてくれるのでは?
A. いいえ。紙の場合と同じく、郵便局は「形式の確認」と「送達の証明」をするだけで、文面の妥当性や法律的な正しさまでは判断しません。そこは利用者の自己責任となるため、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
WEB内容証明の基本的な書き方と流れ
次に、WEB内容証明を使う場合の全体の流れと、文書の書き方のポイントを整理しておきます。ここでは、郵便局HPの説明で分かりにくくなりがちな部分を、できるだけ日常の言葉に置き換えて解説します。
ステップ1:事前準備(アカウントと環境確認)
1. WEB内容証明サービスの利用登録を行う(名前・住所・連絡先などを入力)
2. 支払い方法(クレジットカード等)を登録する
3. 対応ブラウザ・推奨環境を確認し、パソコンと通信環境を整える
この段階でつまずく方が多いので、初めて利用する場合は「登録だけの日」と「実際に文書を送る日」を分けておくと、精神的にもかなり楽になります。
ステップ2:文書の内容をWordなどで下書きしておく
WEB画面でいきなり文章を作り始めると、入力途中で操作ミスが起きたときにすべてやり直しになってしまいます。そこでおすすめなのは、
- まずはWordやテキストエディタで全文を作成しておく
- 一度プリントアウトして読み返し、誤字脱字や表現をチェックする
- 完成した文章をWEB内容証明の画面にコピー&ペーストする
という手順です。「内容の検討」と「WEB画面の操作」を切り離すことで、焦らずに正確な文書を作りやすくなります。
ステップ3:WEB画面でレイアウトを整える
文章を貼り付けたら、システムが自動で行数やページ数を計算してくれます。ただし、改行位置や空白行の使い方によって、見え方がかなり変わります。
レイアウト調整のコツ
- 重要な部分の前後には1行空けて、視認性を高める
- 長すぎる一文は2〜3行で改行し、読みやすさを優先する
- 金額や期日はできるだけ1行の中に収まるよう工夫する
「システム上はOKでも、人間が読むとわかりにくい」状態になっていないか、プレビュー画面で必ず確認しましょう。
ステップ4:送信手続きと控えの保存
内容を最終確認したら、差出人・受取人の住所氏名を登録し、送信ボタンを押せば手続きは完了です。最後に、
- 控え(証明書)のPDFを必ずダウンロードして保存する
- 案件名や日付をファイル名に含め、あとから探しやすくしておく
といった「保存のひと手間」をかけておくと、数年後にトラブルが再燃したときにもすぐに証拠を取り出せます。
郵便局HPがわかりにくいと感じる理由と、その読み解き方
多くの方が口をそろえて言うのが、「郵便局のWEB内容証明の説明ページを読んでも、結局よくわからない」という感想です。その主な理由は次の3つです。
説明が「手続きの流れ」ではなく「機能の一覧」になっている
利用者が知りたいのは「何を、どの順番でやればよいか」ですが、公式サイトではどうしてもサービス仕様の説明が中心になりがちです。そのため、「今日初めて使う人」の目線と「郵便事業者の説明したいこと」のギャップが生じています。
専門用語の定義が一か所にまとまっていない
「様式」「謄本」「配達証明」など、初めての人には耳慣れない言葉があちこちに出てきます。用語集のページはあっても、実際の画面上では意味がリンクされていないため、読みながら調べる手間が多く、途中で疲れてしまうのです。
トラブル時の解説が簡略的
入力エラーや環境トラブルが起こった場合の説明が、「再度お試しください」「推奨環境を確認してください」といった一般論にとどまっていることも多く、具体的にどこをどう直せばよいのかが分かりにくいのも、ユーザーが感じるストレスの原因です。
WEB内容証明が向いている人・向いていない人
最後に、WEB内容証明と紙の内容証明を使い分ける際の目安を整理しておきましょう。
WEB内容証明が向いている人
- パソコン操作やネットサービスの利用に抵抗がない
- 内容証明を継続的に何通も送る予定がある
- 昼間に郵便局へ行く時間が取りにくい
- データで証拠を整理・保管したい
紙の内容証明(窓口)が向いている人
- 一度きりの利用で済みそう
- IT操作が苦手・パソコンをあまり使わない
- 窓口で人に確認しながら進めたい
Q. 最初から行政書士に頼んだ方がいいのはどんな場合?
A. 金額が大きい請求、離婚・不倫など感情的なトラブル、会社同士の取引など、後の裁判や交渉に大きく影響しそうなケースでは、最初から専門家に依頼した方が安全です。WEBか紙かという以前に、「何をどう書くか」で結果が変わる可能性が高いからです。
まとめ:WEB内容証明は「便利だが、自己判断も求められる道具」
WEB内容証明は、時間・場所の制約を大きく減らし、ビジネスや日常トラブルの場面で非常に役立つツールです。一方で、アカウント登録やシステム操作、レイアウト設定など、紙の内容証明にはなかった「ITならではの難しさ」も含んでいます。また、どれだけ便利な仕組みであっても、法律的な内容までは自動でチェックしてくれない点は、紙の内容証明とまったく同じです。
「自分でWEB内容証明を書いてみたいけれど不安もある」という方は、文面だけ専門家にチェックしてもらう、最初の1通だけは代行してもらって操作に慣れてから自分でやってみる、といった段階的な利用方法もおすすめです。
【保存版】e-内容証明で「エラー」を出さないWord設定の黄金ルール
e-内容証明の最大の難関は、会員登録ではなく「Wordファイルのアップロード」です。日本郵便のシステムは書式ルールが非常に厳格で、1ミリでもズレているとエラーになります。
プロが普段設定している「一発で通る設定値」を公開します。
これ通りに設定すればOK!Wordページ設定値
- 用紙サイズ:A4(横置き・縦書き推奨)
- 余白(マージン):上下左右すべて「15mm」以上(推奨20mm)
- フォントサイズ:10.5pt ~ 14pt(推奨12pt)
- フォント種類:MS明朝 または MSゴシック(特殊フォントはNG)
- 文字数制限:1行26文字以内 × 1枚20行以内(※横置きの場合)
- ページ番号:フッターの中央に配置(「- 1 -」の形式)
「髙(はしごだか)」や「﨑(たつさき)」、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ)、丸数字(①、②)などはシステムが読み込めずエラーになります。これらは常用漢字や算用数字(1、2)に置き換えて作成してください。
「郵便局窓口」vs「e-内容証明」どっちがお得?徹底比較
「結局、ネットで出すのと郵便局に行くの、どっちが良いの?」という疑問にお答えします。
結論から言うと、1通だけ出すなら窓口、2通以上出すならe-内容証明、そして「誰にも会わずに・安く出したい」ならe-内容証明が圧倒的に有利です。
| 比較項目 | e-内容証明(電子内容証明) | 郵便局窓口(従来の方法) |
|---|---|---|
| 料金(1枚の場合) | 1,252円 (基本料+電子内容証明料+謄本返送料) | 1,279円〜 (基本料+内容証明料+書留料) |
| 対応時間 | 24時間 365日 | 郵便局の営業時間内 |
| 文字数制限 | 多い(1枚あたり最大1,500文字程度) ※縦置き横書きの場合 | 少ない(1枚あたり520文字) ※26字×20行 |
| 封筒・印鑑 | 不要 | 必要(封筒準備・押印が必要) |
| 手間 | Word設定と登録が少し面倒 | 局員による文字数確認の待ち時間が長い |
【Q&A】e-内容証明の「困った」を解決する10選
当事務所によく寄せられる、e-内容証明に関するマニアックな疑問にお答えします。
Q1. Mac(MacBook)でも利用できますか?
以前はWindowsのみでしたが、現在はMacのブラウザ(Safari, Chrome)でも利用可能です。ただし、Wordファイルをアップロードする場合、Mac版Wordで作成したファイルはレイアウト崩れによるエラーが起きやすいため、PDF変換などはせず、ブラウザ上で直接文章を入力する「かんたん作成」機能を使うのが無難です。
Q2. 写真や図面、PDFなどの資料を添付できますか?
いいえ、できません。e-内容証明で送れるのは「文字情報」のみです。証拠写真や契約書のコピーなどを同封したい場合は、e-内容証明ではなく、郵便局の窓口で従来の内容証明手続きを行う必要があります。
Q3. 相手が受け取らなかった場合どうなりますか?
相手が不在または受取拒否をした場合、差出人(あなた)の登録住所へ返送されます。e-内容証明であっても、この「返送された封筒」自体が「送ったけれど届かなかった」という重要な証拠になるため、開封せずに保管してください。
Q4. 代理人名義(行政書士など)で送ることはできますか?
可能です。差出人欄に「通知人 〇〇 代理人 行政書士 〇〇」と記載することで代理送付が可能です。ただし、アカウント登録者(クレジットカード名義人)と差出人が異なる場合でもシステム上は送れてしまいますが、トラブル防止のため、ご自身のアカウントで作成されるか、専門家に完全代行を依頼することをお勧めします。
Q5. 何枚まで送れますか?
1通あたり最大5枚までです。それを超える長文になる場合は、内容を要約するか、窓口での手続き(枚数制限なし)を利用する必要があります。
Q6. 差出人の住所を知られずに送れますか?
いいえ、e-内容証明のシステム上、差出人の住所氏名は必ず記載され、相手に開示されます。住所を隠したい場合は、e-内容証明の機能ではなく、行政書士に依頼して「事務所住所・行政書士名義」で送る方法(住所秘匿)を利用する必要があります。
Q7. 謄本(控え)はいつ、どうやって届きますか?
発送完了後、数日中(通常3〜4日程度)に、登録した差出人住所へ郵送で届きます。ダウンロード形式ではないため、手元に届くまでは「発送完了メール」を保存しておきましょう。
Q8. クレジットカードがなくても利用できますか?
いいえ、現在のところ支払いはクレジットカード決済のみです。銀行振込やコンビニ払いは利用できません。
Q9. 封筒の色や紙質は選べますか?
選べません。日本郵便が指定する事務的な封筒と用紙で印刷・発送されます。「威圧感のある赤い封筒」などは指定できないため、見た目のインパクトを与えたい場合は不向きかもしれません。
Q10. 自分で送るのと、専門家に頼むのとでは効果は違いますか?
「届く」という意味では同じですが、「相手へのプレッシャー」と「法的リスクの回避」は全く異なります。e-内容証明はあくまで「送るツール」に過ぎません。書く内容(法律構成)に不備があれば、かえって不利になることもあります。「絶対に失敗したくない」場合は、文章作成から専門家への依頼をご検討ください。
「e-内容証明のエラーで進まない…」
「何を書けばいいか分からない」とお悩みの方へ
e-内容証明は便利なツールですが、「書く内容」まで自動で作ってくれるわけではありません。
当事務所では、面倒なWord設定から法的に有効な文章作成、そして発送手続きまでを完全代行いたします。
e内容証明の登録・発送手続きをすべて代行します。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
- 日本郵便株式会社:内容証明 日本郵便
- 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)e-Gov法令検索
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)e-Gov法令検索
- 日本行政書士会連合会ウェブサイト(内容証明に関する情報)日本行政書士会連合会
※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。