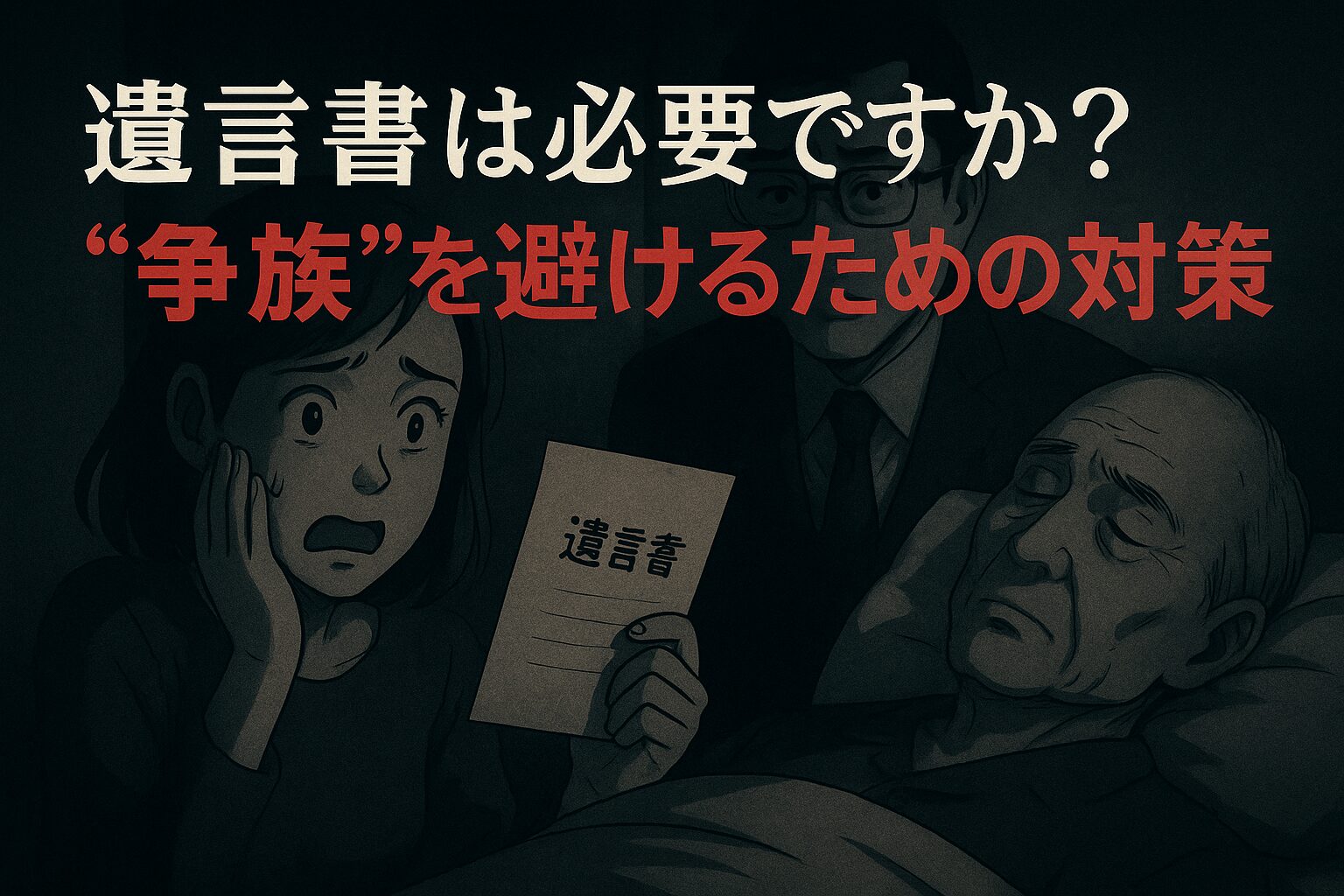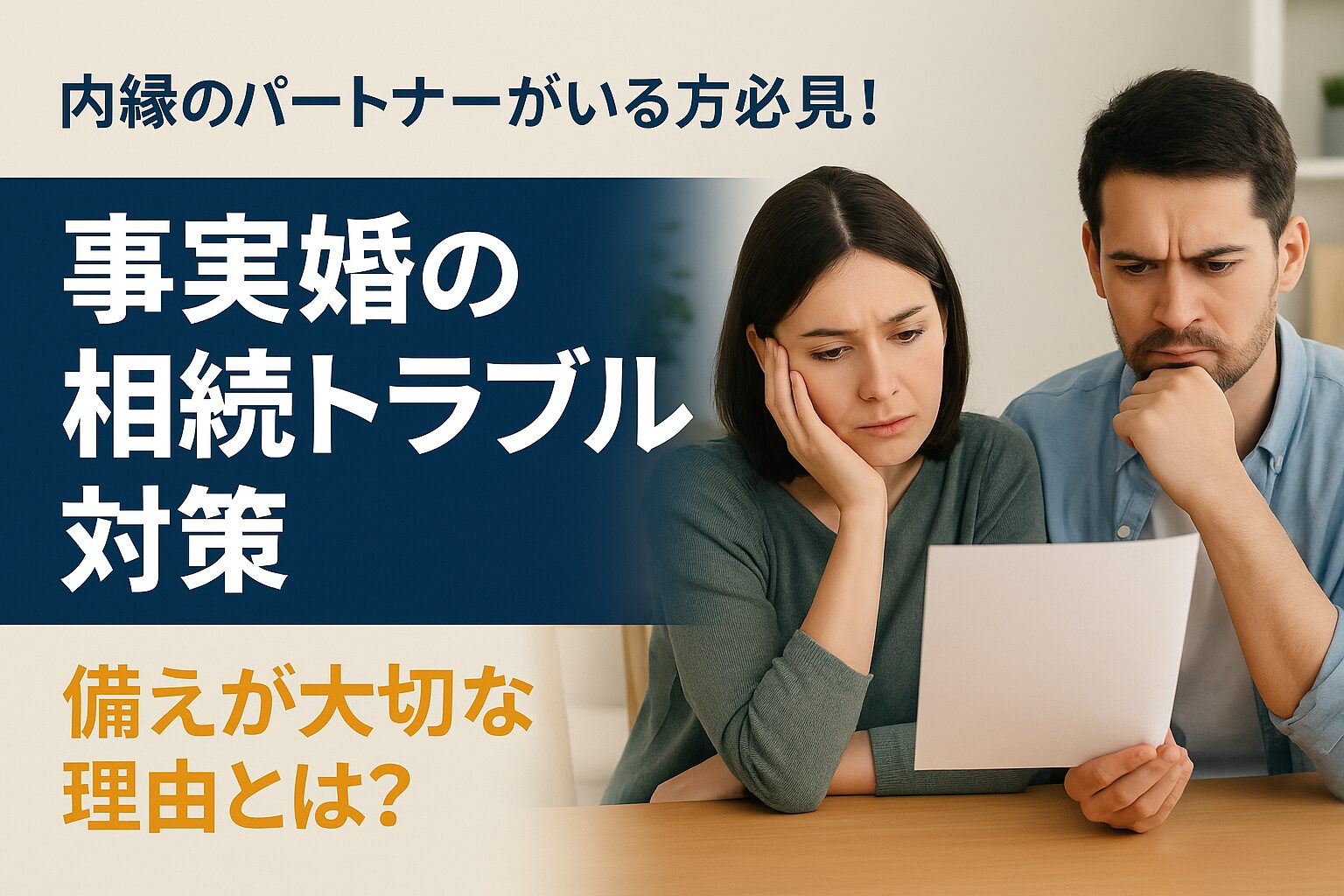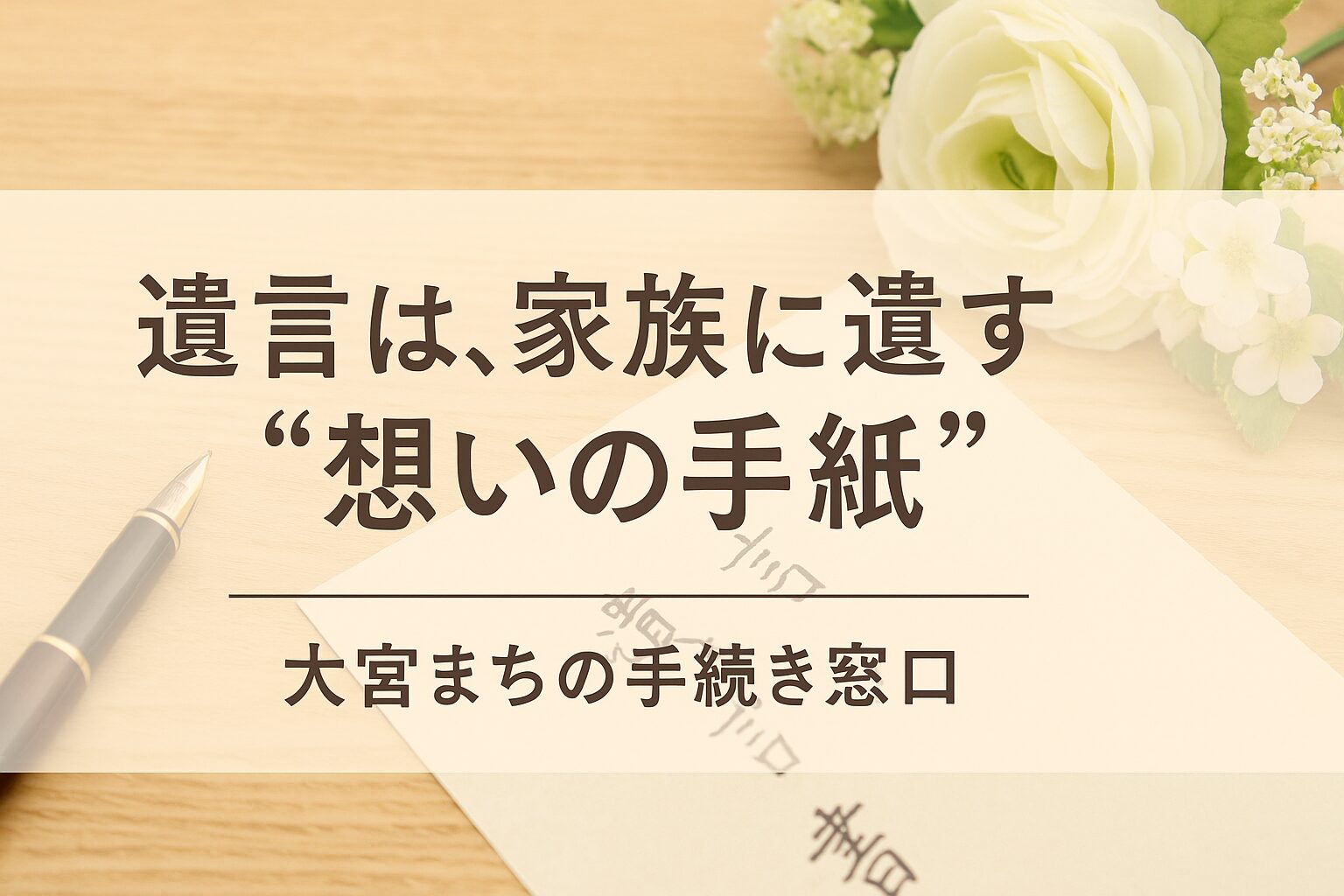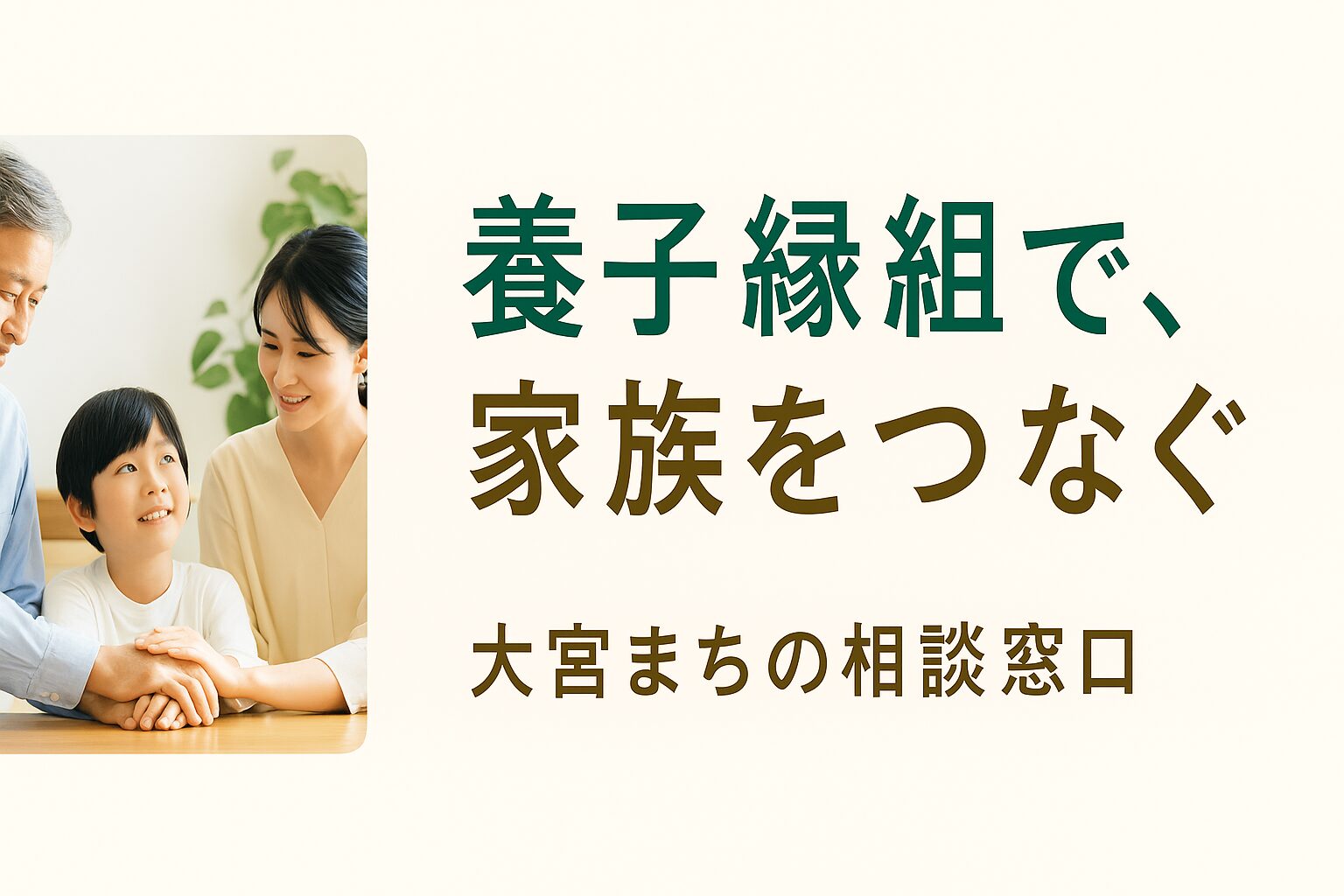養子縁組をすると、相続はどうなる?
養子縁組を行うことで、法的には実子と同じ相続権を持つようになります。
これは、血のつながりがなくても戸籍上の「親子関係」が成立するためです。
実子と養子の相続権は同じ
民法では、養子は実子とまったく同じ立場で法定相続人とされます。
たとえば、実子が1人、養子が1人いる場合、相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。
よくあるトラブル|知らない間に養子がいた!?
相続の際に問題となるのが、「親が内緒で養子縁組していた」パターン。
特に前妻の子や、配偶者の連れ子などが突然、相続人として登場し、実子や兄弟が驚くことも。
- 相続分が変わってしまい、遺産が減る
- 財産の取り分で争いが起こる
- 遺言書がなければ、話し合いが難航
事例紹介:再婚後に養子縁組していたケース
60代の男性が亡くなり、子どもは前妻との間の1人だけのはずでした。
ところが、調べてみると再婚相手の連れ子と養子縁組していたことが発覚。
この養子も法定相続人となり、遺産の分配が2人に。
このようなケースでは、「親の意思はどこにあったのか?」という感情的な対立も生まれやすくなります。
事例追加:再婚・子なし・連れ子を養子にしたケース
再婚夫婦に実子はおらず、再婚相手の連れ子を養子にしていたケース。
被相続人が亡くなった後、その養子となった連れ子が全財産を相続する法定相続人となりました。
しかし、被相続人の兄弟姉妹が「家系の財産が血のつながりのない相手に全て渡った」と納得せず、遺留分侵害額請求を検討する場面もあります。
このように、「子がいない夫婦の再婚と養子縁組」は、特に注意が必要です。
養子縁組を利用した方が良いケース
- 実子がいない場合に、相続の受け皿を用意したいとき
血縁者との関係が希薄な場合、信頼できる人を養子にして財産を託す選択ができます。 - 長年連れ添った配偶者の子に感謝の意を示したいとき
事実婚・再婚での連れ子と強い絆があり、その子へ財産を残したい場合に有効です。 - 事業承継・家業の後継者を法的に守りたいとき
血縁者でなくても事業を任せている相手に、スムーズな承継を行えます。 - 節税対策として養子を活用したいとき
相続税の非課税枠を広げる目的で、1人または2人までの養子が認められています(※制限あり)。
ただし、制度の誤解や目的の不明確な養子縁組は、かえってトラブルのもとになる可能性があります。
実行前には、専門家への相談が不可欠です。
補足:養子縁組と戸籍、相続順位の関係
養子縁組が成立すると、戸籍上でも法定親子関係が形成され、養親の第一順位の相続人となります。
実子とまったく同様に扱われ、相続順位も同じです。
なお、普通養子縁組の場合は、実親との親子関係もそのまま存続します。
つまり、実親・養親の両方の相続人になるケースもあるため、遺産分配の場面では複雑化することもあります。
一方で、特別養子縁組は実親との法的関係が終了するため、実親側の相続権は消滅します(主に未成年者向けの制度)。
養子縁組前後でやっておくべき準備
養子縁組を検討している、あるいは既に養子がいる場合には、以下の対策が有効です:
- 遺言書の作成(誰に何を残すかを明確に)
- 信託の活用(長期的な財産管理の指定)
- 相続人関係図の整理(誰が相続人かを明確に)
まとめ|養子縁組は「相続トラブルの起点」にもなる
養子縁組は家族をつなぐ制度ですが、その一方で相続の権利関係にも大きく影響します。
そのため、「感情」と「法律」両方の視点からしっかり準備しておくことが、家族全員の安心につながります。
不安や疑問がある方は、ぜひ一度、専門家へご相談ください。