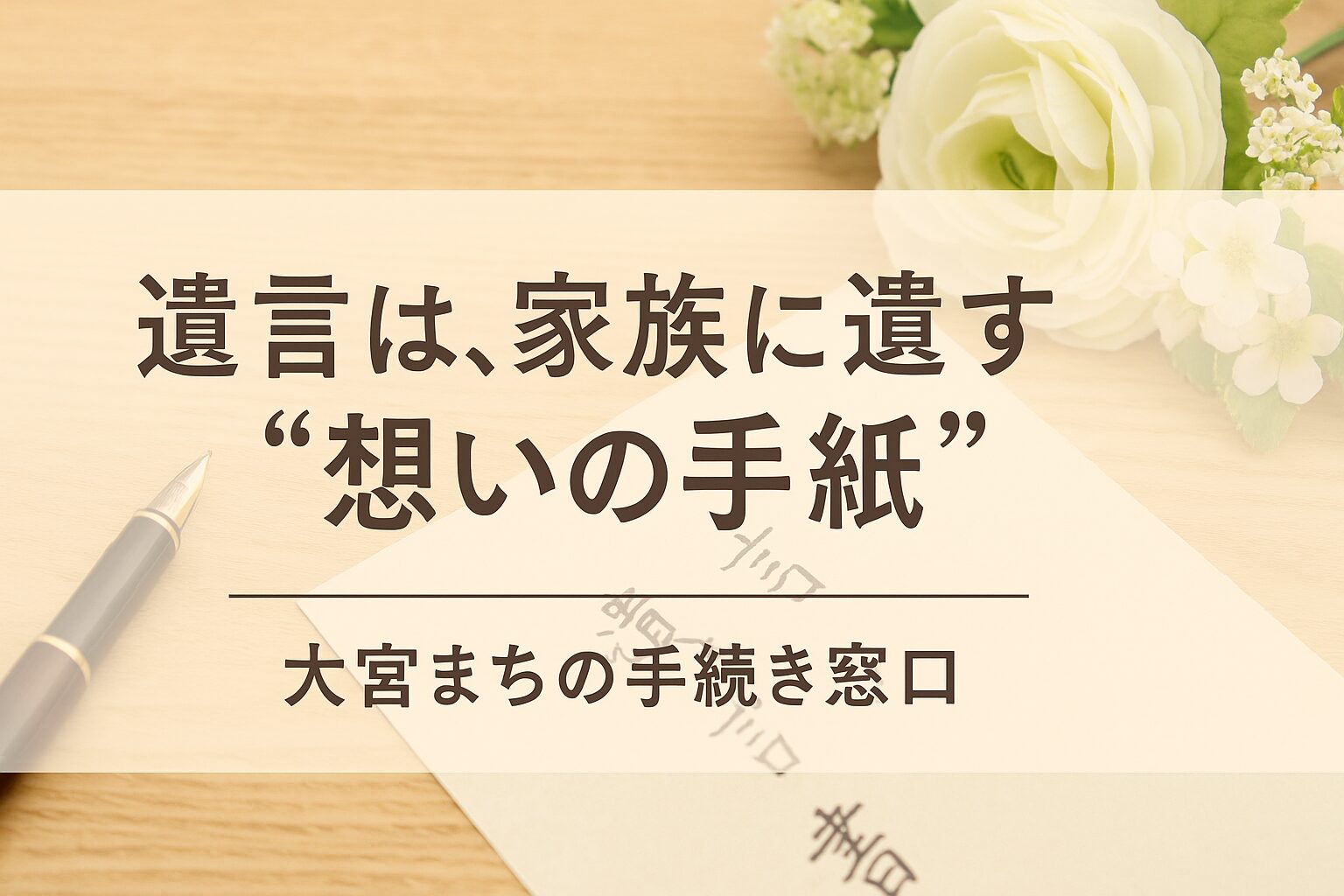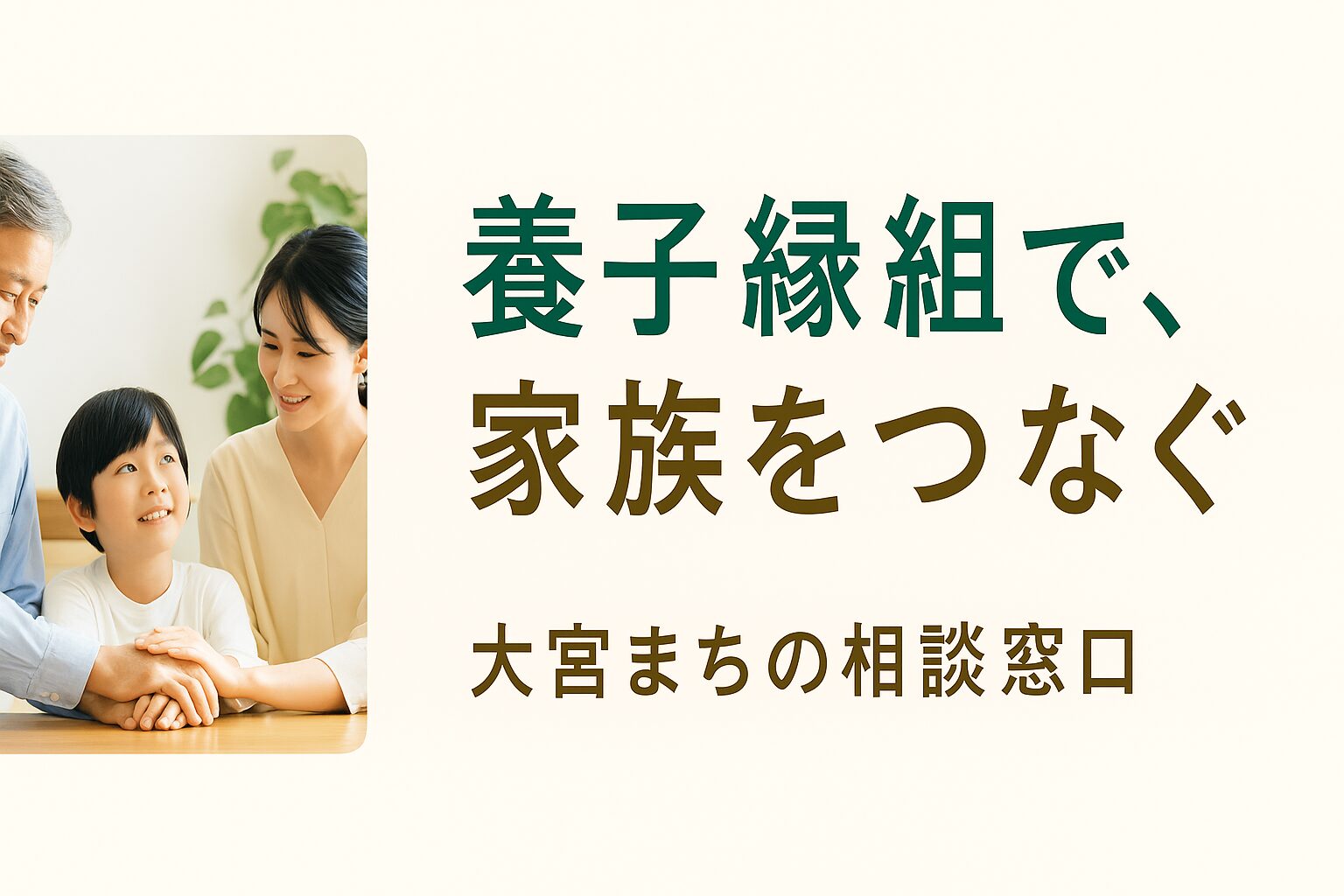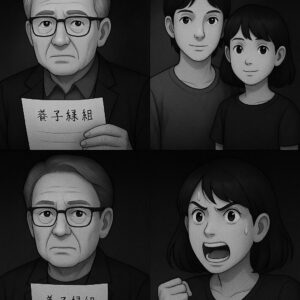ブラック相続シリーズ

連れ子に遺産はゼロ?連れ子と法律上の親子関係
現代では再婚家庭が増え、「連れ子にも遺産は渡せるのか?」という疑問を持つ方が多くいます。血のつながりがなくても長年共に暮らし、親子のような関係を築いた連れ子に何も残せないというのは、感情的にも納得しがたい問題です。本記事では、連れ子と法律上の親子関係、そして相続の実情について具体的に解説します。
連れ子は法定相続人になれない?
日本の民法では、法定相続人は「配偶者」と「血縁関係のある子・親・兄弟姉妹」に限られます。つまり、連れ子とは法律上血のつながりがない限り、そのままでは法定相続人とは認められません。
たとえば、夫が亡くなった場合、妻と連れ子がいても、養子縁組をしていなければ、連れ子には遺産を受け取る権利は発生せず、すべて妻や実子、親、兄弟姉妹に分配されるのが法律上の原則です。
養子縁組をすれば、連れ子も実子と同じ相続権を持てる
連れ子に遺産を確実に渡すためには、養子縁組が有効な手段となります。養子縁組が成立すれば、連れ子は法律上「実子」と同等の地位となり、相続権を持つことが可能になります。
成人との養子縁組は、家庭裁判所の許可なく市区町村へ届け出るだけで成立します。未成年との場合は親権者の同意など一定の条件がありますが、そこまで複雑な手続きではありません。
養子縁組をしないとどうなる?
養子縁組を行わない限り、連れ子と法的な親子関係は認められず、「他人」として扱われます。たとえ感情的には家族同然であっても、法律的な根拠がないため、相続権は発生しません。
このため、いざ相続が発生したときに、連れ子に遺産が渡らず、実子や親族との間で争いになる可能性も十分にあります。実際に「面倒をみてきたのに報われない」というケースは後を絶ちません。
遺言書で連れ子に遺産を残す方法
養子縁組をしなくても、「遺言書」を作成することで連れ子に遺産を残すことは可能です。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実性やトラブル防止の観点からは公正証書遺言が推奨されます。
形式や署名、日付など法律で定められた要件を満たす必要があるため、専門家の助けを借りることで、トラブルのない遺産分割を実現しやすくなります。
連れ子への生前贈与という選択肢
生前贈与は、相続とは異なり、自分の意志で自由に財産を渡す制度です。連れ子への思いを生前に形にしたいと考える方にとって、有効な手段といえます。
ただし、贈与税や不公平感による他の相続人とのトラブルなど注意点もあります。特に高額な財産を贈与する場合には、専門家のアドバイスを受けながら進めることが安全です。
実際にあったトラブル事例
70代のAさんは、妻の連れ子と20年以上一緒に暮らし、家族同然の関係を築いていました。しかし養子縁組をしていなかったため、Aさんの死後、遺産はすべてAさんの兄弟へ渡ってしまいました。
連れ子は介護も看取りも担っていたにも関わらず、一円も相続できませんでした。遺言書もなかったため、法的な救済手段もなく、深い悲しみと不満を残す結果となりました。
まとめ:想いをカタチにする準備を
連れ子に遺産を残すことは、単なるお金の話ではなく、「共に生きた証」を残す大切な行為です。養子縁組・遺言・生前贈与のいずれかを準備することで、後悔のない未来を築くことができます。
家族のかたちは多様化しています。血縁だけでは測れない家族関係だからこそ、自分の想いや感謝をきちんと伝える手段として、法的な準備を今から始めてみてはいかがでしょうか。