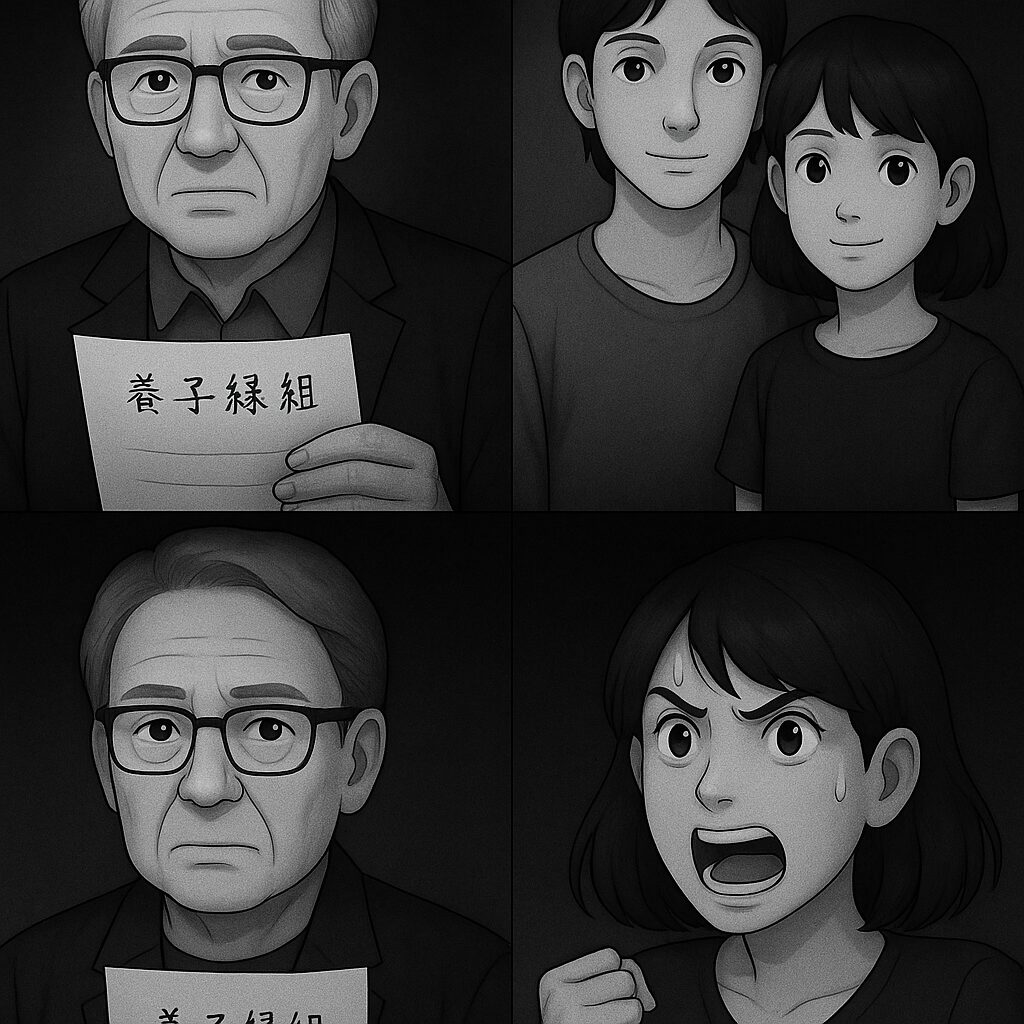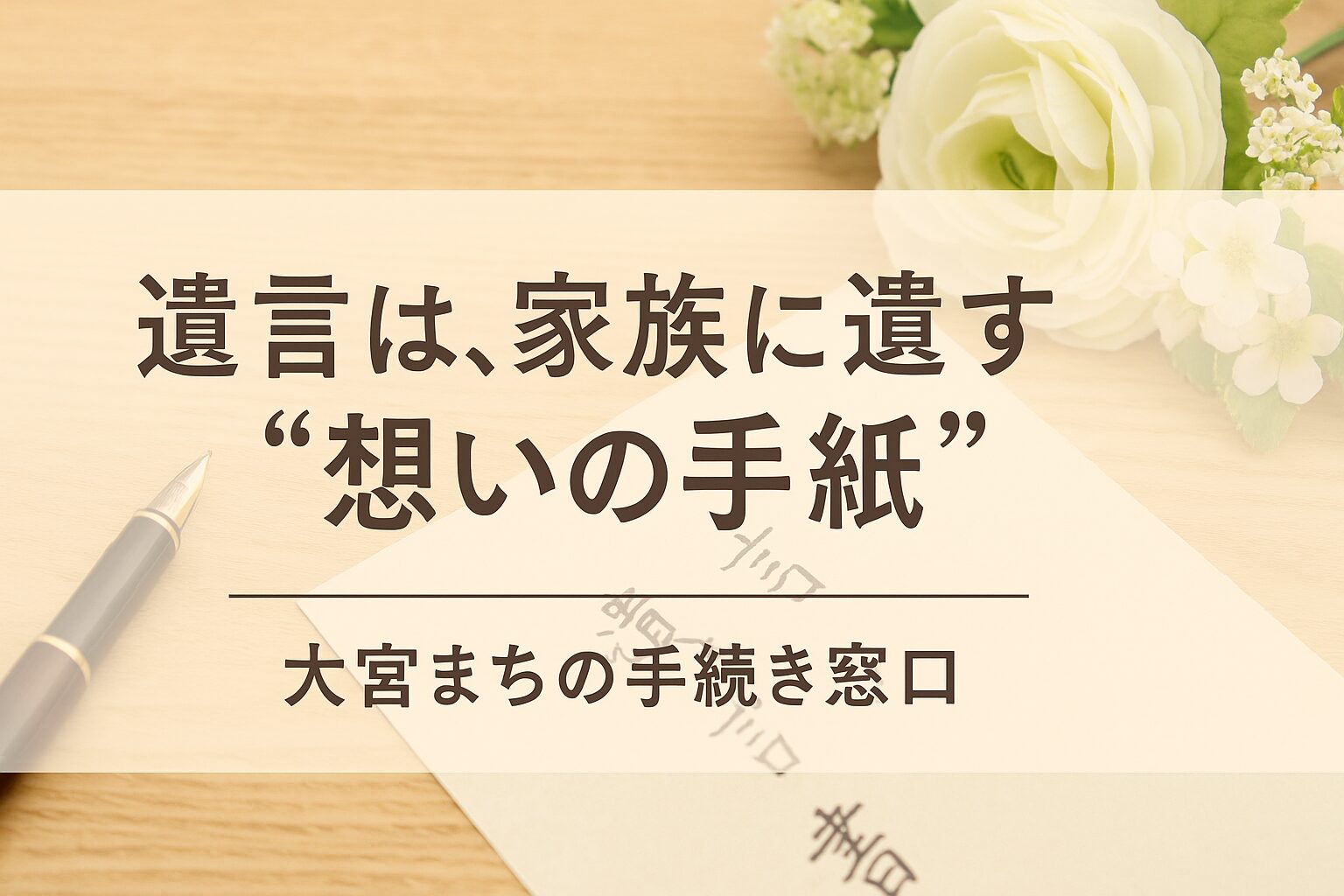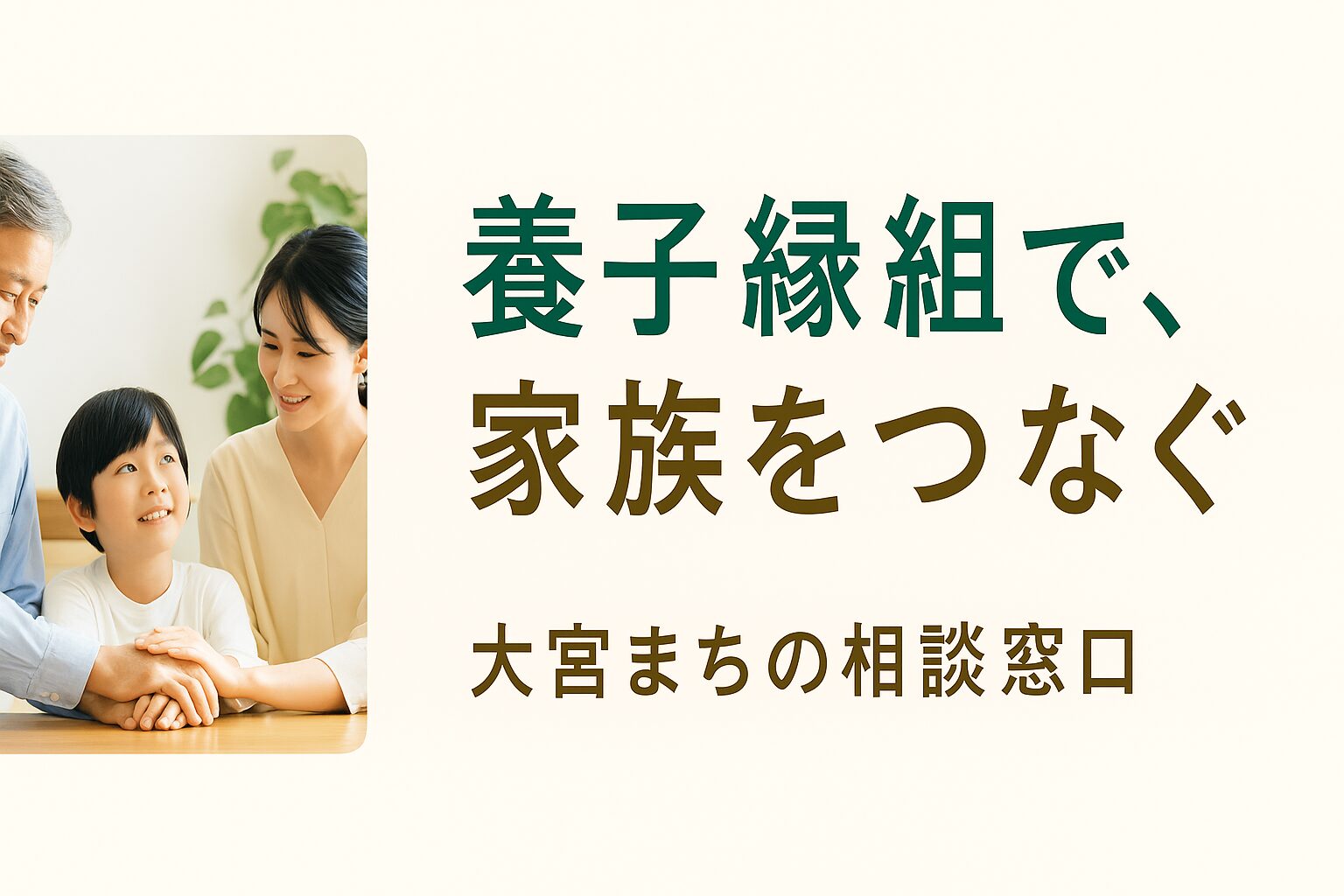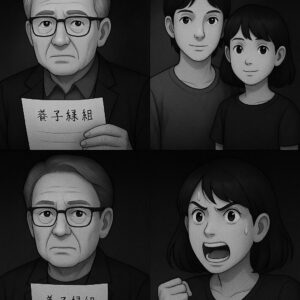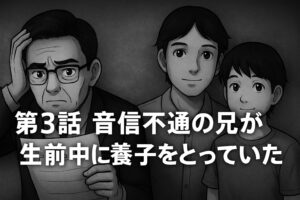ブラック相続シリーズ

第5話 養子の連鎖|子のいない親族間での“節税養子ラッシュ”
これは、相続の現場で実際に起きた「養子の連鎖」にまつわる物語です。被相続人が子のいない高齢者である場合、親族間での節税対策として養子縁組が連鎖的に行われることがあります。今回のケースでは、その養子縁組が思わぬ争いを生んでしまいました。
財産を守るための“戦略的養子縁組”が、かえって家族間の疑心暗鬼や対立を引き起こす結果になったのです。表面的には節税の工夫に見えても、その背景には相続に対する複雑な思惑が絡んでいました。
◆ 背景:被相続人は子のいない伯父
伯父・Aさんは生涯独身で子どももいませんでした。長年教職に就き、まじめで几帳面な性格だったといいます。退職金や貯蓄により、亡くなった際に残された財産は約3000万円に上りました。
直系の子どもがいないため、相続人となり得るのは、兄弟姉妹やその子どもたち(甥や姪)でした。法的にみればスムーズに相続できるケースのはずが、ある人物の登場によって状況は一変します。
◆ ある日、突然「養子だった」と名乗る人物が
法定相続人の一人である甥・Bさんが遺産分割協議の準備を進めていたところ、別の甥・Cさんが「実は伯父Aさんの養子になっていた」と名乗り出ました。確かに戸籍には養子縁組の記録がありました。
驚いたBさんは親族に確認を取りましたが、誰もその事実を知らなかったといいます。Cさんが養子になった時期や背景は謎に包まれており、家族内では「何か裏があるのでは」と疑念が生まれ始めました。
◆ 養子が優先される?法定相続人との関係
民法では、養子は実子と同様の法定相続権を持ちます。つまり、他の甥姪たちよりも優先的な地位に立つことができます。この場合、相続人は養子のCさんのみとなり、他の相続人は排除される可能性があるのです。
仮に他に相続人が複数いたとしても、被相続人と養子の関係が優先されるため、養子が単独で相続することも十分にあり得ます。この制度は本来、子のいない家庭の救済策ですが、誤用・悪用されるとトラブルの火種になります。
◆ 背後にあった“節税養子ラッシュ”
さらに調査を進めると、なんと他の親族も複数の高齢親族と養子縁組を結んでいたことが発覚しました。目的は明らかに相続税対策。税法上、養子の人数によって基礎控除額を増やせる仕組みがあるため、それを利用していたのです。
しかし、その結果として、養子となった側とそうでない側で「得する人」「損する人」が生まれ、感情的な対立を招くことになりました。節税が目的だったとしても、親族の間で信頼が揺らぐリスクを孕んでいます。
◆ 解決への対応策
- 養子縁組の時期や状況に不自然な点がないか確認
- 家庭裁判所で「無効」を主張する余地があるか検討
- 弁護士・行政書士を交えて冷静な遺産分割協議を行う
また、遺言書があれば「養子にすべてを渡す」などの希望も記載できるため、トラブルを避けやすくなります。相続対策は“制度の裏側”も見据えた慎重な設計が必要です。
◆ 専門家の視点
養子縁組には法的効力が伴いますが、その背後に不正や違法性がある場合は、争点となり得ます。高齢者の判断能力や意志が適切に確認されたかも重要です。特に認知症や意思確認が曖昧な状況での養子縁組は、後に無効主張される可能性があります。
少しでも疑問がある場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。節税や相続対策であっても、“倫理”と“法”の両方を見極めながら対応する姿勢が大切です。